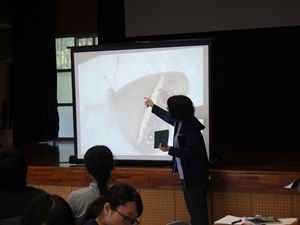中学3年 科学研究チャレンジプログラム「西表野生生物調査隊」 Vol.2
サイエンス
次は、白浜班の活動を4日目の合流までご紹介します。
【白浜班1日目】
船浦班と別れた後、バスは国道を南に走り国道の終点である白浜に着きました。いよいよ、白浜での調査活動が始まります。
まず旧国道を登り、避難路を確認しました。山の上から見える西表の海、海人の家の景色が素晴らしく、皆で立ち止まって眺めました。
その後、公民館の館長さん、海人の家の管理人さん、お世話になるスタッフの方々にご挨拶です。
荷物整理の後、夕食の時間となりました。ハヤシライスをおいしく頂きました。
【白浜2日目】
今日はカヌーを漕いで仲良川河口へ行き、マングローブ林を調査しました。
風がとても強い日で、なかなか進まない!そんな中でも誰一人あきらめず、1時間程かけてようやく河口にたどり着きました。マングローブを間近で、触れながら観察することができました。船の上で昼食をいただき、さらにカヌーで一番川へ入って調査を続けました。
帰りは選手交代、行きに船で仲良川河口まで来た人が、今度はカヌーを漕いで海人の家を目指します。途中干潟上陸しました。泥の中に手を入れたら貝やナマコがいたり、そーっと砂を見つめていたらカニが動いていたり…みんなで話し合いながら様々な生物を観察しました。
交流会に向けて歌の練習をし、夕飯をいただいた後は夜間調査に出かけました。なんと!上空にヤエヤマオオコウモリを観ることができました。耳を澄まし、目を凝らして周りを観察しました。暗闇に光るヤエヤマホタルは、幻想的でとても美しかったです。帰り道ではサキシマハブも見つけてびっくりしました…!
明日もいろいろな場所で調査をします。しっかり寝て備えましょう…。
【3日目】
3日目はホシズナ海岸へ行き、ホシズナの採取を行いました。みんなで一斉にホシズナをビンにすくい入れます。
そのあと、海にいる生物調査をしました。岩に海水がたまった潮だまりに、小さな生物がたくさん!みんな一生懸命観察していました。ミルソーを使って小さな魚も捕まえることができました。
お昼に冷製パスタをいただいて調査を再開したら、しばらくしてスコールのような雨が降ってきました。急いでテントへ避難。テントの中でも生物の様子を観察したり、歌を口ずさんで時間を有効に使います!
雨が少し弱くなったので、浦内川のジャングル調査に出発。様々な場面での調査・研究を経験する、貴重な機会となりました。
歩いていると、セマルハコガメの赤ちゃん、ヒカゲヘゴなど、海では見られなかった生物も観察できました。炭坑の跡も見学し、当時の生活の様子を垣間見ることもできました。
海人の家に戻った後は、東海大学 河野先生、水谷さん、学生お二人から講義を伺いました。学生の國島さん、黒澤さんからは、サンゴの白化がサンゴの被度等に及ぼす影響に関して、水谷さんからは、ウミショウブの減少とウミガメの増加に関してお話を伺いました。研究の手法、進め方、発表の仕方など、これからの研究活動、明日に控えた成果報告会につながることをたくさん学ばせていただきました。講義の後は夕食を一緒にいただきました。女性であり、学生として研究をなさっているお二人からは、進路を決めたきっかけなどを伺うことができました。
【4日目 合流前】
今日はいよいよ船浦班と合流の日です。荷物をまとめてから、朝は白浜港に釣りをしに出かけました。
サクラエビをエサにして、じっと糸が引くのを待ちます。しかし…魚は見えているのに、なかなか釣れません。夕方の交流会でいただく魚は無しかもしれません。
お手伝いをしてくださっていた斉藤さんが、捕まえたカニをエサに釣竿を海に入れたところ、1分ほどで大きなクロダイが釣れました!最終的に、2、3人の人が魚を釣ることができました。もっと技術を磨いて、たくさん釣れるようになりたいと思いました。
海人の家に戻った後は、ひたすら歌の練習に励みました。
【4日目 白浜班・船浦班 合流後】
4日目正午ごろ、歌の練習をしている白浜のメンバーに船浦のメンバーが合流しました!歌声も力強くなりました。
お待ちかねの昼食は「八重山ソバ」です。
そして今年度の調査報告会が始まりました。白浜班、船浦班と異なる場所での調査活動では、どのような生物たちに出会えたのでしょうか?
なぜその生物を選んだのか、どこでどのような状況で見つけたのか、どのような特徴があるのかなど、現地で野帳にメモした情報を基に全員が発表しました。評価表に互いの発表についてまとめながら真剣に聴きました。
終了後、近くの金城旅館の方から頂いたピタンガを試食しました。
シャワーの後は、楽しみにしていた交流会です。
今年は、地元青年会の皆様の他、隣の白浜小学校や中学校の皆さんと共に交流のひと時を過ごしました。
準備が済んでご挨拶です。そして和気あいあいにバーベキューが始まりました。
お腹も膨れて、いよいよ互いに用意してきたものの発表です。
初めは、子供会の皆さんのエイサーです。真剣な演技と、迫力のある太鼓の音に皆引き込まれ、心が揺さぶられました。次は青年会の皆さんの歌と演奏です。島特有の三線の音色と歌声にみな酔いしれました。三線の旋律が変わり、カチャーシーの始まりです。手の動きを教えて頂きいざスタート。初めは恥ずかしそうにしていた生徒達も舞台に上がって白浜の皆さんと楽しく踊りました。
次は、生徒達からお礼の合唱をお届けしました。
「校歌」と「道」の合唱を皆さんが真剣に聴いて下さいました。
最後に一家でご参加下さった琉球大学渡辺先生のお嬢さんに指ハブの作り方を教えて頂き、よいお土産ができました。
【5日目】
今日は、イダの浜でのシュノーケリングです。朝食後に大掃除を済ませ、フェリーに乗って舟浮港に向かいました。

しっかり食べよう
舟浮集落は、西表島の固有種であるイリオモテヤマネコが最初に発見されたところです。集落から丘を越え、イダの浜に到着しました。
チーム分けの後、チームごとにシュノーケリングのスタートです。今年度は例年になく気温が低く、海水は冷たかったのですが、あっという間に慣れて泳ぎ始めました。
昼食はホットドックです。皆たくさんお代わりをして鋭気を養いました。
昼食後は、浜の生物の観察です。
そして午後のシュノーケリングでは、各班沖合まで移動しサンゴ礁や魚類をはじめ様々な生物の観察をしました。

大自然に抱かれ、様々な生物に出会った5泊6日。大雨の中のトレッキング等困難なこともありましたが、友人と共に乗り越え、いつしかクラス全体が一つにまとまりました。
皆、この活動を支えて下さった全ての方々に感謝しつつ、ここで身に付けたたくさんの力をこれから始まる科学研究チャレンンジプログラムの研究活動に活かしていくことでしょう。

トゥドゥマリ浜にて