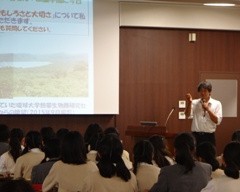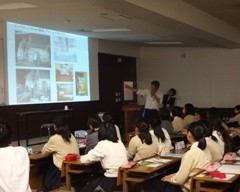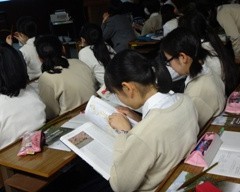SI便り マングローブのおもしろさと大切さ
山脇の学び
4月19日(火) 「マングローブのおもしろさと大切さ」と題して馬場繁幸先生の講演がありました。
馬場先生は、琉球大学をご退任されてから国際マングローブ生態系協会(ISME)の理事長、海外では、ISMEの事務局長を務めていらっしゃいます。
今回は、これから5月に初めて西表島を訪れる中学3年生科学研究チャレンジプログラムの「野生生物調査隊」メンバー54名と、SIクラブの希望者、そして今回の講演会を企画してくださった、琉球大学の渡辺信先生のお声かけで、都立科学技術高校、都立両国高校、都立立川高校でマングローブの研究に関わっている生徒の皆さんも共に講演に参加しました。
実際に見て触わることがとても大切だと、大きなトランクからたくさんのマングローブの胎生種子を、生徒たちに渡され、みな細長いその姿をじっくり触り観察しながら、先生のお話を伺いました。また、様々な果実や茎、根、そしてマングローブ協会が出版されている本もたくさん見せて下さいました。
先生はアジアの国々を中心に、マングローブ調査や植林を行ってこられた話を、パワーポイントのたくさんの映像を見せながら、また絵を描きながらお話くださいました。
先生の講演を聞いて、これから西表島を訪れる生徒達にとっては、これからの調査活動がより身近で、興味深いものになったのは言うまでもありません。生徒たちは、お土産のメヒルギやオヒルギ、ヤエヤマヒルギの胎生種子を手に、「家に帰ったら植えよう!」と嬉しそうでした。
次の日は、琉球大学の渡邉信先生が、いらして科学研究チャレンジの研究活動の時間を使って、これから出発する「野生生物調査隊」が、対象の特徴をしっかり捉えて撮影できるよう「写真の撮り方」の説明をしてくださいました。実際どのような生物の写真が撮れるでしょうか、楽しみです。