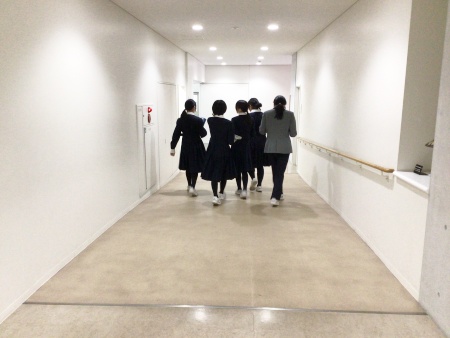2024年度 中学校高等学校の終業式を行いました
学園便り
3月21日(金)、中学校高等学校の終業式を行いました。
校内では、穏やかな春の暖かさにたくさんの小さな命が芽吹き始めています。


終業式は中学・高校別に行われました。学校長式辞の後には、ご退職される先生方とのお別れもあります。


感謝を込めて一礼

中学校終業式【学校長式辞】
おはようございます。
今朝校門に立ち、一年の月日の速さとみなさんのご成長を感じていました。
皆さんがこの一年をつつがなく過ごし、健やかにご成長されたことを嬉しく思います。
学年末にあたり、昨年の4月に私からお伝えした生徒目標を振り返ってみましょう。「礼節・協働」「チャレンジとアクション」「自走・自治・俯瞰」でしたね。
これは、中高6学年同じ生徒目標なのですが、これらの項目で期待する行動は、全学年同じではありません。昨年より今年、今年より来年、高いレベルで考え行動することを求めています。
経験を重ねるたびに、学びとして書き込まれたことは、ものの見方・捉え方に変化をもたらします。その意味では年を経るごとに、より高くより深く、考え行動することが期待されます。同じ生徒目標でも学年に応じて、求められる行動は異なっているということです。
中1生は何事も初めてでしたが、今年一年の経験の様々は、あなたのメモリにしっかりと記憶できていますか。中2生は1年前の経験を活かし、より高いパフォーマンスを目指して行動できましたか。そして2年分の学びをあなたのメモリに記憶できていますか。いつでも取り出して次の経験に活かせるようにしておいてください。
3学期には、この一年の締めくくりといえる大きな学園行事が二つありました。
一つは合唱祭、一つは山脇サイエンスエキスポ(YSE)です。
合唱祭。中学3学年が一堂に会し、各クラスが一年間紡いできた時間を、ステージでのたった数分で歌声に乗せて出し尽くす。今も皆さんの歌声が耳によみがえるような、珠玉の時間でした。
あなたの心に響いた歌声とともに、あなたのクラスがどのように臨んだのか、そこに自分がどう関わり、何に貢献できたか、ということを是非メモリに書き込んでおいてください。
YSE。先輩たちの個性あふれる探究の取り組みや、生き生きと発表する姿を見て、何を受け取りましたか。先輩たちの「志の宝箱」から、あなたの心に引っかかったものをメモリに残してほしい、そしてこれからの探究テーマを考えるヒントにしてほしい、と思います。
またYSEは2日間、多くの生徒保護者や研究者や大学の先生が来校され、大盛況でした。その企画準備は高校生を中心とした生徒たちの手で行いました。行事の成功の裏には、誰がどんなことをしてくれていたのか、想像してほしいと思います。上級生になるということは、受け身から“創り手”になっていくということだからです。
さて中高6年間は、人生で最も心身の変化が大きい時。だからこそそこに関わる先生たちは、時に驚いたり感動したりすることの連続です。この成長は何によってもたらされるのだろう。心と行動をつかさどる脳の発達に秘密があるのではないか、そう考え、認知心理学の視点からみてみると、やはりみなさんの成長や行動の特徴には、脳の発達が深くかかわっていることがわかります。まさにみなさんの年代の12歳から14歳くらいからが、脳の機能に大きな変化が始まる時期なのです。
脳の目の奥のほうにあたる場所に「扁桃体」という部分があるのですが、これが成長ホルモンの影響でこの時期から非常に活性化されるそうです。扁桃体は人の生存に関するとっさの判断を下す大切な場所ですが、活性化すると不安や恐怖・怒りといったネガティブな感情が起きやすくなるのだそうです。「そういえば最近、以前よりイライラしたり不機嫌になったりしやすくなったかも」なんてご自身や周りの友達で心あたりを感じませんか。
一方、この扁桃体をコントロールして感情を抑える機能を持つのが、脳の前部分にある「前頭前野」です。思考や創造性を担い、人を人たらしめる中枢部分といわれる場所ですが、ここは成熟が最も遅い部分で、扁桃体よりも少し遅れて発達する。直感的な感情をつかさどる部分が先に急激に発達し、理性的な判断をする部分が後からゆっくり発達するというわけです。その差によって、中学時代は感情の起伏や心の悩みが起きやすくなると言われます。脳の発達の構造と深い関係があるんですね。
すべては脳のせいだから仕方ない、と言いたいのではないのです。そのような発達の仕組みや人間の体や心について理解できると、日常の自分や他者についての悩みの様々も、冷静に見つめることができるようになります。「私だけじゃないんだ」と思うことで、理解しがたかった友達の感情も違った視点で受け入れられるかもしれません。その年代にいる自分や仲間を理解し慈しみ合いながら、互いの成長につなげていってほしい、と思います。
みなさんの「前頭前野」はこれからさらに発達していきます。以前お話しした「メタ認知」(俯瞰して自分をコントロールする力)は、ここがつかさどっている能力ですから、みなさんは日々確実に、他者の感情を理解したり、対人関係を処理したり、自分と他者を俯瞰する広い視野を身につけていきます。高校生の先輩、すごいなあと皆さんが感じるのは、先輩たちは認知の発達とともに、学園生活で重ねてきた様々な経験から学んで行動に結びつけているからなのですね。
ところで、脳は20代前半でほぼ完成しますが、前頭前野だけは緩やかにずっと成長し続けるのだそうです。脳は成長のピークを過ぎれば衰えるばかりだと考えていた私にとっては、朗報でした。記憶力や視覚聴覚といった機能は衰えても、知識と経験を使いこなす知恵や、豊かな人間性をつかさどる部分は、いくつになっても成長し続ける…年を重ねることの意味がここにあると思います。
ただし、前頭前野の発達には次のような心掛けが必要だそうです。「人と交流をすること」「創造的な活動をすること」「たっぷり睡眠をとり、体を動かすこと」「バランスの良い食事をとること」
今から心がけていれば、人生にわたって豊かな脳の発達を促すことができますね。脳と心と体の関係は、みなさんの成長と認知の発達を知る上での、私の重要な探究テーマの一つになっています。
4月の始業式に、アメリカの著作家ジョン・カルヴァン・マクスウェルの言葉を紹介しました。年度の最後にもう一度彼の言葉を贈ります。
「どんな経験も最高の教師。立ち止まって内省することで経験は見識に代わり、より深みのある人生を生きていくことができる」
「つらい経験をしたとしても立ち直り、成長した自分に出会える人と、いつまでもそこにはまって抜け出せない人の違いは、“問題にどう立ち向かうか”その心構えの違いにある。」
失敗も後悔も全部自分への学びにして、まるごと携えてまた前へ進みましょう。私も先生方もまた、皆さんの心身の発達を支援しながら、ともに学び成長し続けていきたいと思っています。
今年度最後の一日、お世話になった先生方、共に過ごし学び合った仲間への感謝を伝えられる時間にしてください。
式の後は大掃除。1年間使用した教室や廊下、特別教室などを次の学年が気持ちよく使えるように心を込めて磨き上げます。




HRでは全体への連絡や締めくくりの後、担任の先生からひとり1人成績表が手渡されます。今年ついた力を来年ももっと伸ばせるよう、一緒に確認していきます。




屋外実験場ではつくしも顔を出しました!春はもうすぐそこです。